 くろと
くろとねぇグリーンリーブ、万博行ってきたんだけどさ、意外と外国人少なくない?てか、ほとんど日本人だったんだけど!



えー!外国の人がいっぱい来ると思ってたのに?



くろと、すいれん、そう感じたのは当然かもしれませんね。私も実際に足を運んでみて、同じような印象を受けました。
今回は、万博会場で「なぜ日本人がこれほど多いのか」「外国人の姿が少ないのはなぜか」という疑問について、私の見解を交えながら詳しくお話ししていきましょう。
日本人がほとんど
大阪・関西万博の会場に足を踏み入れてみて、最初に強く感じたのは、来場者のほとんどが日本人であったということです。
もちろん、国際的なイベントですから、少数の外国の方もいらっしゃいましたが、私の肌感覚としては「スタッフ以外の外国人を見かけることはほとんどなかった」と言っても過言ではありません。
比率で言えば、9割以上が日本人ではないかと思うほどでした。
公式発表などでは、国際博覧会における外国人来場者の比率が10%や12%といった数字が示されることもありますが、実際に現地で感じたのは、その半分、もしかすると5%にも満たないのではないかという印象でした。



ちなみに12%の数字がどれぐらい多いかだが、日本人来ている人が少なくない?というぐらいの肌感覚でわかるぐらい多い。



そうなの!?
これは、単に私がたまたまそう感じただけでなく、会場内の案内表示や飲食店のメニュー、あるいは来場者同士の会話の内容など、あらゆる側面で日本語が中心の空間が広がっていたことからも裏付けられます。
海外からの友人と来場したとしても、まるで国内の大きなイベントに来たかのような感覚に陥ってしまうかもしれません。
万博という「国際博覧会」のイメージとは、少し異なる現実がそこにはありました。



外国の言葉、あんまり聞こえなかったもんね。なんか、日本のお祭りみたいだったよ。



ええ、まさにその感覚ですね。良くも悪くも、非常に「日本らしい」雰囲気だったと言えるでしょう。
なぜ日本人が多いのか?
では、なぜ万博会場はこれほどまでに日本人が多く、外国人の姿が少ないのでしょうか。
これにはいくつかの要因が複雑に絡み合っていると考えられます。
まず場所が近さ
当然のことながら、自国で開催されるイベントである以上、日本人が最も多く来場するのは自然なことです。
物理的な距離が近い分、交通費や移動にかかる時間も少なく、気軽に足を運ぶことができます。
しかし、それだけではありません。日本が「島国」であるという地理的な特性も、海外からの来場者が増えにくい一因となっていると言えるでしょう。
海外から日本へ来るには、飛行機や船といった手段しかありません。
欧米諸国からは特に、航空券代が高額になる上に、移動時間も長くかかります。
近隣のアジア諸国からであれば比較的アクセスは容易ですが、それでもやはり、大陸続きの国々で開催される万博と比べると、心理的・物理的なハードルは高いと言わざるを得ません。
例えば、ヨーロッパで開催される万博であれば、陸路で国境を越えて多くの国の人が訪れることが可能です。
しかし、日本の場合はそうはいきません。この「島国」という特性が、海外からの大々的な集客には不利に働いている側面があるのです。



じゃあ、外国の人は、飛行機に乗るのが大変だから来ないの?



そうですね。飛行機のチケット代も高いし、時間もかかるから、なかなか来づらいという事情も
1970年以来の思い出が強い
もう一つの大きな要因として、日本人にとっての「万博」に対する特別な思い入れが挙げられます。
特に、1970年に大阪で開催された日本万国博覧会は、当時の日本人にとって非常に強いインパクトを残しました。
戦後の高度経済成長期を象徴するイベントであり、未来への希望を強く感じさせるものでした。
その時の感動や記憶は、親から子へ、そして孫へと語り継がれ、多くの日本人の心の中に「万博=特別な場所」というイメージを植え付けています。
そのため、今回の大阪・関西万博は、単なる新しいイベントというだけでなく、「あの時の感動をもう一度味わいたい」「子供や孫にも万博を見せたい」といった、郷愁にも似た期待感を持って来場している方が多いように感じられます。
これは、海外の多くの人々が持たない、日本人特有の来場動機と言えるでしょう。
くろと:うちのおじいちゃんも、1970年の万博の話、よくしてたなぁ。太陽の塔がすごいんだって!
グリーンリーブ:そうですね。あの万博は、多くの日本人の心に深く刻まれていますから。今回の万博にも、そうした「思い出」や「期待」を抱いて来場されている方が多いでしょう。
そもそも思っていたより人少ない
万博会場を実際に歩いてみて感じたのは、想像していたよりも来場者が「スカスカ」だという印象でした。



特に朝とか空いていたわ
1970年代の万博は広さもあってか人数は少なく感じるが、そもそも2.2倍近い330ヘクタールの面積もあるので人数で見ればかなり少ないと言える。
もちろん、まったく人がいないわけではありませんが、東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンのような混雑とは程遠く、むしろゆったりと歩けるレベルでした。



特にリングの上とかは日中は歩きやすいよ
それでも敷地面積が非常に広いため、全体的に人が分散しているという要因もありますが、それでも「こんなものか」と感じてしまうほどでした。
大阪の心斎橋などの繁華街の方が、明らかに人が多く混雑していましたね。



あれ渋谷とか新宿に来たのかと思っていたぐらいすごかった。
この「思っていたより人が少ない」と感じる背景には、いくつかの理由が考えられます。
娯楽化が主な要因?
一つは、現代の「娯楽の多様化」です。スマートフォンやゲーム、動画配信サービス、メタバースなど、自宅にいながらにして楽しめるエンターテインメントが溢れているため、わざわざ高額な入場料を払って万博に足を運ぶという選択肢の優先順位が下がっている可能性があります。



YouTubeでどんな感じか見ちゃうから、もういいや、ってなる人もいるのかな?



まさにその通りです。また、YouTubeなどのSNSや、最近ではメタバースといった仮想空間でも、万博の会場の雰囲気や展示内容がリアルタイムで発信されています。
これにより、「実際に行かなくても、ある程度の情報は得られる」という感覚が広まり、来場を躊躇する要因になっている可能性も否定できません。
1回万博で行ったらもう十分。
さらに、万博の敷地は非常に広大で、半分の面積しか使っていないにもかかわらず、一日で全てを回りきることは困難ですが
内容が内容でそのため、「一度行けば十分」と感じる人が多いのも、来場者数が伸び悩む一因かもしれません。



そういえばTITAN様もメタバースがどんなもんか見れば十分と言っていたわ
多くの人にとって、万博は「新しい発見や体験」を求めて行く場所ですが、その期待感が、入場料や移動時間に見合うほど満たされないと判断されれば、リピーターは増えにくくなります。
1970年の万博こそはSNSもなかったのもあるけど、それを実現したとしても当時の技術で考えればなんども生きたくなる要素ばかりです。
あとはやはり同じような感じも飽きてしまうのもあるかもしれません。



これは万博に限らず商店街とかも同じ店ばかりのもあるな
外国から見れば大阪付近は観光名所がとにかく濃くて多い


海外からの観光客の視点に立つと、大阪とその周辺地域は、非常に魅力的な観光名所がコンパクトに集中しているエリアです。



東に行けば「奈良」
北東に行けば「京都」
西に行けば「神戸」
南に行けば「和歌山」
がある。
東京に比べてエリアが狭い分、移動時間が少なくて済み、効率的に多くの場所を巡ることができます。
そのため、短期間の滞在で日本の文化や歴史、グルメを満喫したいと考える外国人観光客にとっては、万博よりも既存の観光地が優先される傾向にあると言えるでしょう。



実際に奈良公園とか心斎橋とか行ってみたけど、万博より外国人の数が圧倒的に多かったもん!



大阪の繁華街や、京都の清水寺、奈良の大仏など、明確な目的と期待を持って訪れることができる場所は、依然として高い人気。
これらの観光地は、写真映えする景観、伝統的な文化体験、そして「日本食」という、海外からの観光客にとって非常に分かりやすい魅力を持っています。
万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」は、抽象的で理解に時間がかかるため、限られた滞在時間の中で、より明確な観光体験を求める外国人にとっては、選択肢として後回しになりやすいのかもしれません。
つまり、万博は「旅のついでに寄る場所」ではなく、「万博そのものが旅の目的」となるほどの強い磁力が必要なのかもしれません。
現状、その磁力が、他の有名観光地に比べて弱いという課題があると言えるでしょう。
インバウンドは終焉に差し掛かり始めた
万博に限った話ではありませんが、日本を訪れる外国人観光客(インバウンド)の流れにも、変化の兆しが見え始めています。
私も奈良公園などの有名観光地を訪れた際、以前に比べて外国人の数が減っているような印象を受けました。



えー!お外の人来なくなっちゃうの?



ゼロになるわけじゃないけど。これまでのような爆発的な増加傾向は落ち着きを見せ始めているということだな
これにはいくつかの理由が考えられます。
円安ピークは過ぎた
まず、「円安のピークが過ぎた」ことが挙げられます。
かつての極端な円安は、外国人観光客にとって日本での旅行費用を非常に安く抑えられるという大きなメリットをもたらしましたが、その状況が変化しつつあります。
また、日本へのインバウンド観光が長く続いてきたことで、特にリピーター層の間では「ある程度の体験はし尽くした」という「飽き」も生じている可能性があります。



確かにどこの国も似たようなものですから、ある程度すぎると飽きるのも納得するような・・・
さらに、国際情勢の変化も無視できません。
例えば、アメリカのトランプ大統領が掲げる「アメリカファースト」のような保護主義的な政策は、世界経済のブロック化を促し、国際的な人の移動や交流を抑制するきっかけとなる可能性があります。
日本国内でも「日本ファースト」を掲げる政党が出始めているため、これが具体的な政策として実用化されると、円の価値や国際関係にブレが生じ、外国人観光客の足がさらに遠のく可能性も指摘されています。
もちろん、これらはあくまで見解ですが、万博の国際的な集客を考える上では、こうしたマクロな視点も必要になってくるでしょう。
日本人がほとんどだ!



なんか、思ったのと全然違ったけど、それもそれで面白いね!



すうん!日本のお祭りみたい!



そうですね。改めてまとめますと、大阪・関西万博は、現時点では「ほとんどが日本人によって楽しまれているイベント」という印象が非常に強いです。
公式の数字と肌感覚にギャップはありますが、これは日本ならではの地理的・歴史的要因、そして現代の娯楽の多様化、さらにはインバウンドを取り巻く国際情勢の変化が複雑に絡み合った結果だと考えられます。
国内のイベントとして見れば、多くの日本人来場者が、新しい展示やパビリオンに目を輝かせ、友人や家族と楽しんでいる姿は、十分に魅力的です。
価格についても、食事はやや高めですが、飲み物に関しては比較的良心的で、飲食物の持ち込みも可能であるため、工夫次第で出費を抑えることができます。
運営を支えるスタッフの方々も熱心に業務にあたっており、日本のホスピタリティを感じさせる場面も多々ありました。
国際的な視点から見ると、まだ多くの課題や伸びしろはありますが、まずは日本国内で万博の魅力を最大限に高め、その熱気が海外にも伝播していくことが重要なのかもしれません。
これからの万博がどのように変化し、進化していくのか、引き続き注目していきましょう。

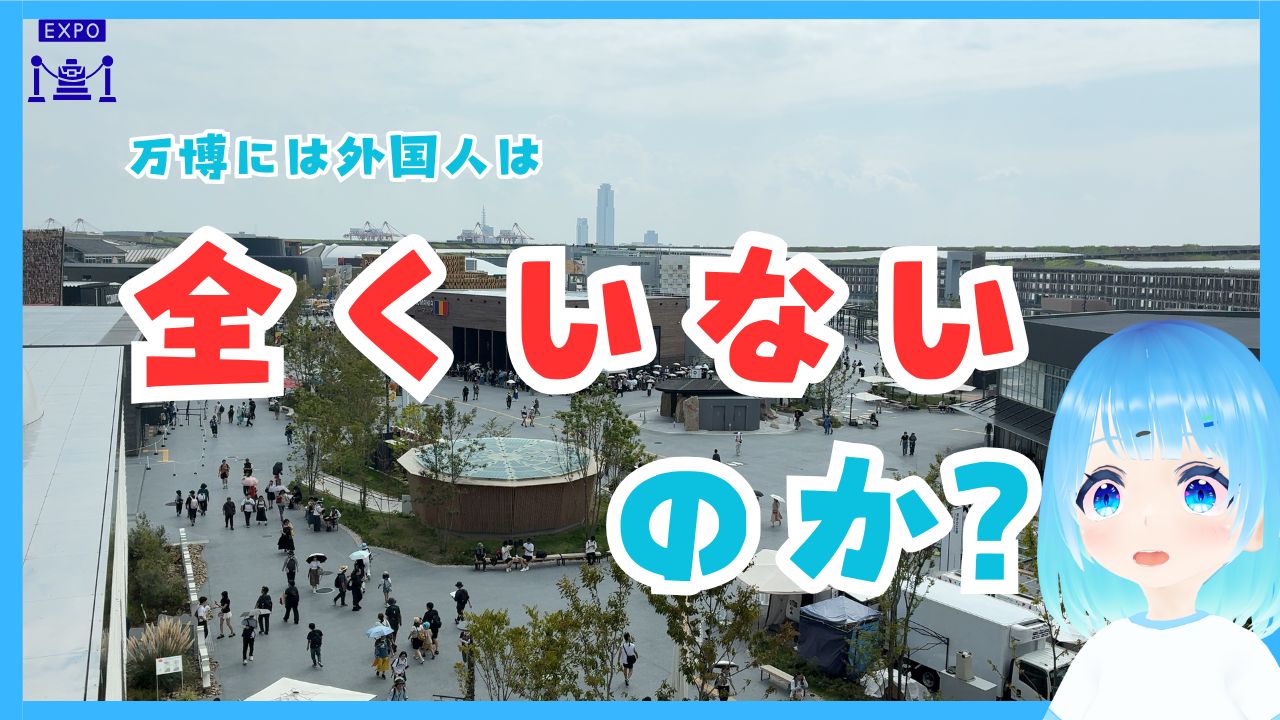
コメント(誹謗中傷禁止)